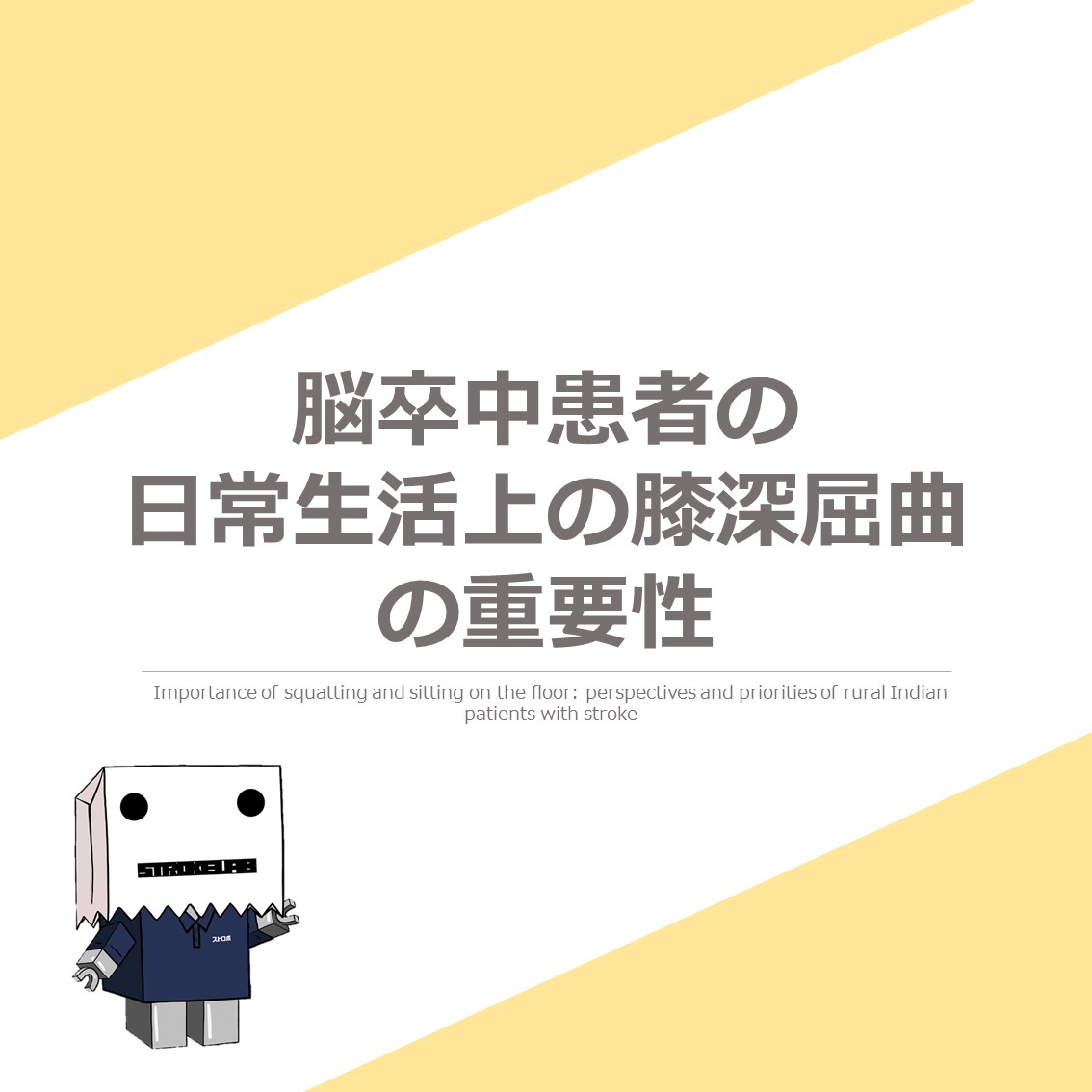【2023年版】脳卒中者に対するトレッドミル訓練の効果とは?通常歩行練習の違いまで。
脳卒中後のトレッドミル訓練の効果は?

STROKE LABでの免荷式トレッドミル訓練場面
免荷式トレッドミルトレーニングの負荷量は?
片麻痺のある脳卒中患者の無重力トレッドミルでの典型的な除荷速度は、部分体重支持トレッドミル トレーニング (BWSTT) とも呼ばれますが、患者の個々のニーズに応じて異なります。 ただし、いくつかの一般的なガイドラインを提供できます。
関連性の高い論文は?
カテゴリー
タイトル
●脳卒中者に対するトレッドミル訓練の効果とは?トレッドミル歩行と通常歩行練習の違い(トレッドミル部分の抜粋)
なぜこの論文を読もうと思ったのか?
●一般的に免荷あり又はなしでのトレッドミル訓練が行われるようになっている。基本的にどのような効果が見込まれるのか整理をすべく本論文に至る。
内 容
背景
●脳卒中者の65%~85%は、脳卒中後6か月までに自立して歩くことができるが、歩容の悪化は慢性期を通じ持続する。 6分間歩行テスト(6MWT)で測定される歩行の持久力は、慢性期脳卒中患者の中で最も困難と印象付けられる領域です。脳卒中患者は、他のすべての活動と比較し、リハビリの時間をウォーキングの練習に費やしている。歩行能力の向上は、リハビリテーションを受けている脳卒中の人や、地域社会で脳卒中を患っている人が最も頻繁に挙げる目標の1つです。
●文献では、ウォーキングを改善するための課題指向トレーニングの主要なアプローチとして、体重免荷を提供するハーネスシステムの有無にかかわらず、トレッドミルトレーニングが挙げられる。歩行持久力、機能強化、バランス機能等が様々な速度要件を組み込むことで提供される。
●トレッドミルトレーニングのメリットは、神経生理学的基盤がある可能性がある。脊椎動物はトレッドミルにて促進される交互の四肢の動きから脊髄神経回路の協調的な活性化が示されている。トレッドミルの練習は、多くのステップを通じ麻痺側下肢を「強制使用」することもでき、その結果、より速い速度での麻痺側筋の負荷と活性の量が増加します。最後に、体重免荷システムを備えたトレッドミルは、従来の治療法では安全に監視することができない低機能の患者も早期歩行練習が開始できるようになる可能性がある。
トレッドミルでの治療・効果
●脳卒中患者のトレッドミルストレステスト中の自己選択歩行速度と歩行の持久力(6MWT)は、最大酸素摂取量(VO2peak)と相関し、心機能に関連している。
●Moseleyは、脳卒中後の15のトレッドミルトレーニングRCTを含むメタ分析を実施し、トレッドミルトレーニング(体重免荷ありまたはなし)と他の理学療法による介入間で歩行速度または歩行関連のデータに統計的差異はないと結論付けた。BWSTTよって歩行を速く歩くことは、歩行が自立した片麻痺患者にとって重要でない傾向でした。しかし、トレッドミルトレーニングは少なくとも他の歩行介入と同じくらいの効果があった。
● Van Peppenは歩行持久力において3つのBWSTT RCTの有意な標準化された効果サイズ(30%の平均変化)を報告したが、これは歩行速度またはその他の歩行カテゴリでは有意ではなかった。
● Teasellは、BWSTTの6つのRCTとBWSTTのない2つのRCTのシステマティックレビューにおいて、BWSTTの有無にかかわらずトレッドミルトレーニングが標準的な治療よりも歩行パフォーマンスを向上させるという相反する証拠があると結論付けた。トレッドミルトレーニングをサポートするエビデンスは矛盾しているようですが、最近の診療ガイドラインでは、BWSTTを脳卒中の介入として含めることを推奨している。
●トレッドミルトレーニング(体重免荷ありまたはなし)を同量の理学療法または遅いトレッドミルトレーニングと比較した3つの慢性期脳卒中患者を対象とした研究のメタ分析は、歩行速度に大きな影響を与えた事が報告された。
●身体的支援なしで歩くことができる脳卒中の人に、BWSTTを速いまたは最大の歩行速度で適用した場合、遅い速度または従来の歩行トレーニングでのBWSTTよりも効果的であるといういくつかの証拠がある。
●BWSTTがより多くの歩数を促進するという点でメリットを提供する可能性があるが、地面での歩行トレーニングは、歩行に必要なさまざまなコンポーネントに挑戦するためのより自然な刺激を提供する。地面での歩行を成功させるには、反応的な制御に加え、予測的な姿勢制御(他の人に注意して歩く、障害物を越えるなど)が必要です。視覚的流れ・変化や椅子に座る、方向転換をする他様々な要素が加わりながら訓練出来る事もトレッドミルと違い通常歩行にてメリットのある部分です。
●最適なトレーニングは、トレッドミル訓練と様々な課題を含んだ通常歩行訓練の組み合わせかもしれません。
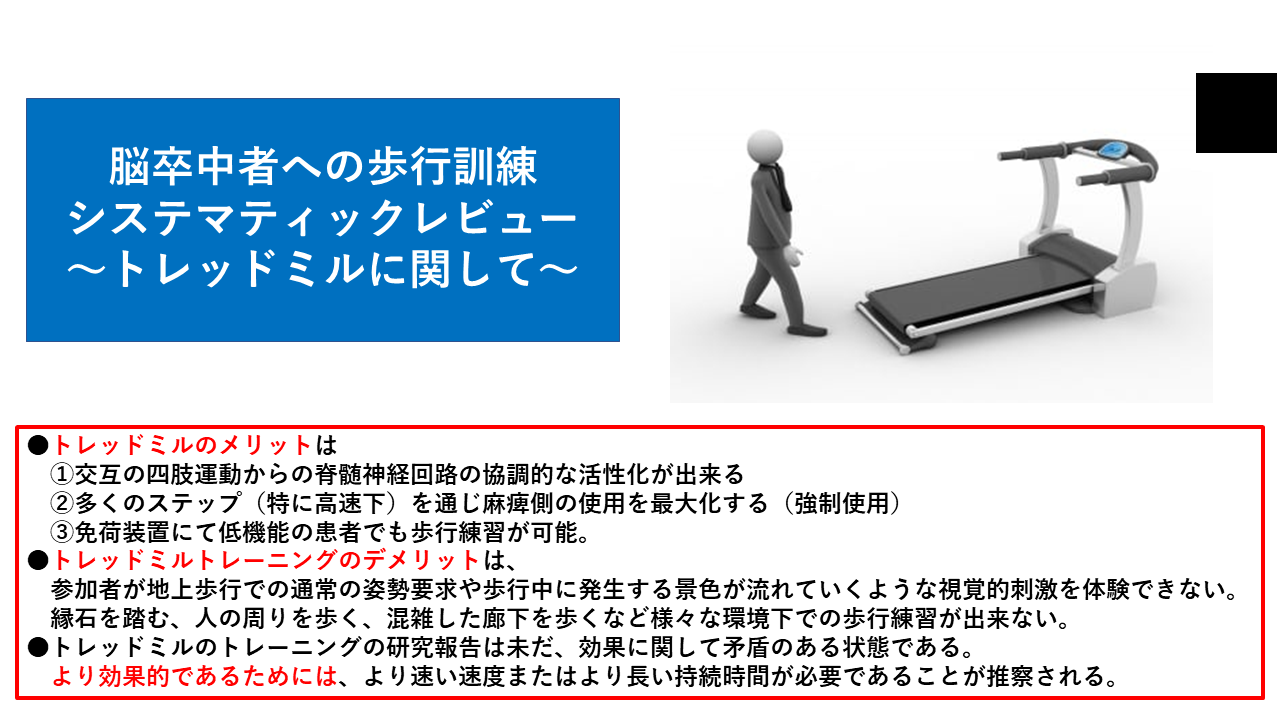
私見・明日への臨床アイデア
●トレッドミルにおいても、その欠点を補う映像を駆使した、視覚的流れや応用歩行、視覚的・聴覚的cueを提供できるものも出てきている。トレッドミルでは、本論文にあるように、免荷が行えることで重度麻痺の患者でも歩行が可能、床が動く事で強制的かつ速い速度での交互性歩行の促通が可能である。運動量の担保としても良いかもしれない。何となくトレッドミルで歩くのであれば、様々な環境変化、人や視覚の流れなどが含まれた通常の歩行練習の方が効果的かもしれない。目的を持ち臨床に挑みたい所である。
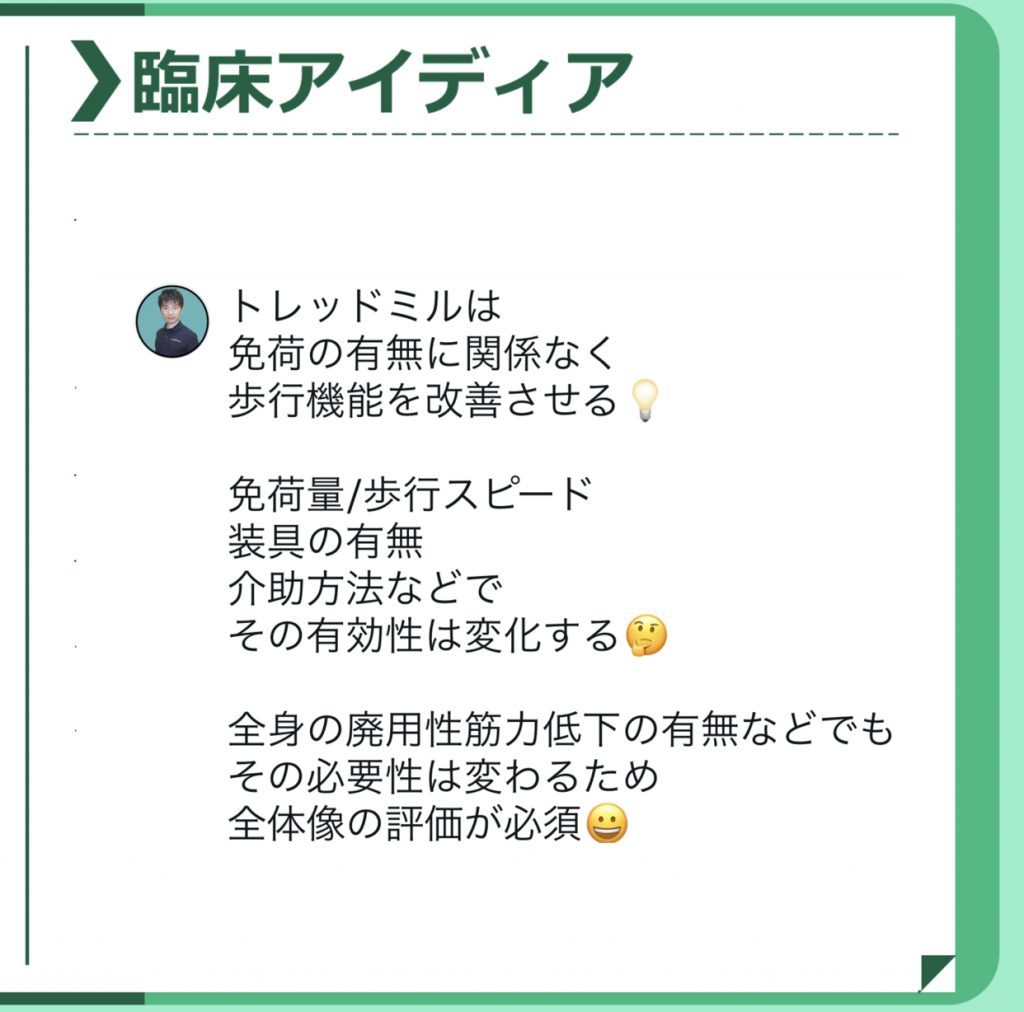
下肢・歩行のハンドリングに役立つ動画
https://youtu.be/ObeFqDpO0vE
脳卒中の動作分析 一覧はこちら
塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)