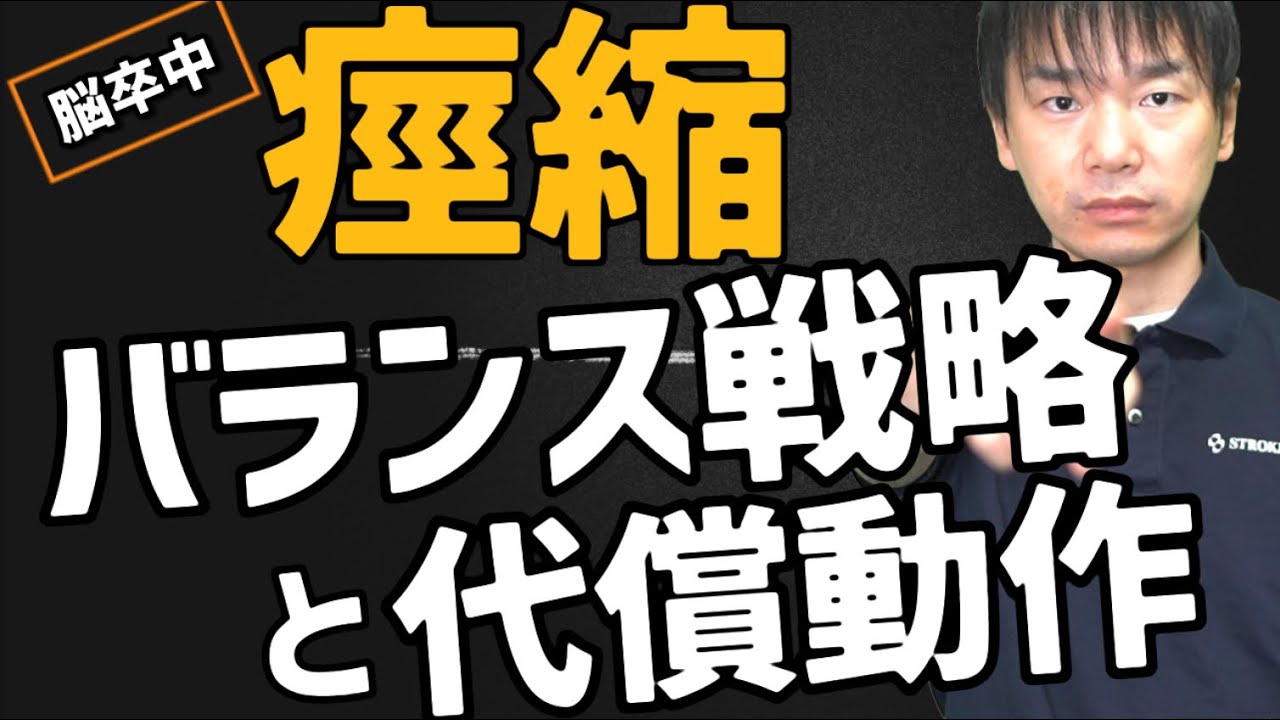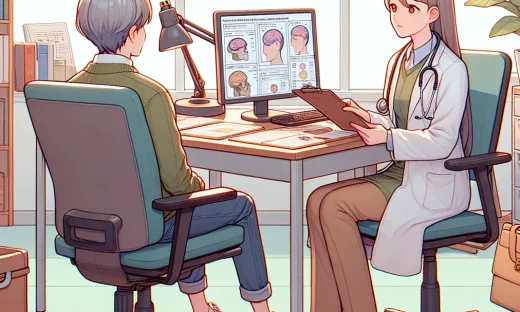【2024年】実例!パーキンソン病の転倒の原因と対策、体操まで紹介 リハビリ論文サマリー
STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!
論文を読む前に:事前知識
ここでは、本論文のテーマであるパーキンソン病の転倒の原因について、講義形式でおさらいしたいと思います。
パーキンソン病の転倒の原因についての講義
登場人物
- 新人療法士: 石川さん
- 医師: 田中先生(神経内科およびリハビリテーション専門医)
ストーリー
カンファレンスルームでの対話
石川さんは、リハビリテーションの新人療法士として、田中先生の講義に参加しました。今日のテーマは「パーキンソン病患者の転倒の原因」についてです。特に運動症状と認知症の側面から詳しく説明します。
講義の開始
田中先生は、パーキンソン病患者が転倒しやすい原因について、最新の研究論文を基に説明を始めました。
田中先生: 「石川さん、今日はパーキンソン病患者がなぜ転倒しやすいのか、その原因について詳しく見ていきましょう。まず、運動症状と認知症の二つの側面から考えます。」
運動症状による転倒の原因
1. 姿勢反射の障害
田中先生は、まず姿勢反射の障害について説明しました。
田中先生: 「パーキンソン病では、姿勢反射の障害が主な転倒原因の一つです。正常な姿勢反射は、バランスを保つために体の位置を自動的に調整する機能ですが、パーキンソン病患者ではこの機能が低下します。その結果、軽い外的刺激や急な動作に対してバランスを崩しやすくなります。」
2. 歩行障害
次に、歩行障害について詳しく説明しました。
田中先生: 「パーキンソン病患者の歩行は、すくみ足や小刻み歩行といった特徴があります。これらの症状は、歩行中に突然動けなくなったり、前傾姿勢で歩幅が狭くなり、バランスを崩しやすくなることから、転倒のリスクを高めます。」
3. 筋肉の固縮
田中先生は、筋肉の固縮についても説明しました。
田中先生: 「筋肉の固縮も転倒の一因です。特に下肢の筋肉が硬直すると、スムーズな歩行や姿勢の調整が難しくなります。この固縮は、体の動きの自由度を制限し、ちょっとした障害物や不安定な地面でのバランス崩しやすくします。」
認知症による転倒の原因
1. 注意力の低下
田中先生は、認知症による注意力の低下について説明しました。
田中先生: 「パーキンソン病に伴う認知機能の低下は、特に注意力の低下に影響します。これは、周囲の環境を適切に認識する能力が低下し、潜在的な危険に対して適切に反応できなくなることを意味します。例えば、床の段差や障害物に気づかずに転倒するリスクが高まります。」
2. 視空間認知障害
次に、視空間認知障害について詳しく説明しました。
田中先生: 「視空間認知障害も転倒の重要な原因です。これは、自分の体の位置や動き、周囲の物体との関係を正確に認識できなくなる状態です。例えば、ドア枠や家具を避ける際に適切な距離感が取れず、接触して転倒することがあります。」
3. 実行機能の低下
田中先生は、実行機能の低下についても説明しました。
田中先生: 「実行機能の低下は、計画的な動作や判断力に影響を与えます。日常生活での移動や動作の計画がうまくいかず、不適切な動きや遅れた反応が転倒につながることがあります。」
まとめと今後の展望
田中先生は、講義のまとめとして今後の展望について話しました。
田中先生: 「石川さん、今日お話しした運動症状と認知症の二つの側面からの転倒原因を理解し、それに応じたリハビリテーションプランを提供することが重要です。最新の研究を活用し、個々の患者に合った転倒予防対策を強化していきましょう。」
石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございました。これからのリハビリテーションにおいて、今日学んだ知識を活かしていきたいと思います。」
論文内容
カテゴリー
歩行、神経系
タイトル
パーキンソン病と転倒:ビデオ録画による実際の転倒の記録
引用文献
Falls and Parkinson’s Disease: Evidence from Video Recordings of Actual Fall Events.
?PubMed Weaver, T. B., J Am Geriatr Soc. 2016 Jan;64(1):96-101.
なぜこの論文を読もうと思ったのか?
・転倒の瞬間を実際に見ることは少なく、どのように転んだかは常に推測せざるを得ないものと考えていたが、本研究は高齢者施設に住む方々の転倒の瞬間を録画し分析しているため、この論文の知見を活かすことでパーキンソン病患者様の転倒時の様子をより確かなものに出来るのではないかと思ったため。
内 容
目 的
・パーキンソン病の有無による転倒の特性の違いを実生活の録画から分析すること。
方 法
・2つの高齢者施設に住む被験者306名(パーキンソン病群16名、コントロール群290名)。
・2007-2013年の間、共有スペースと居室(同意を得た上で)の被験者の生活を録画した。
・転倒は職員の報告をもとに発見され、ビデオ分析された。
・転倒の定義は「意図せず床、地面などの低いところに接触すること」だった。
・転倒はfall video analysis questionnaireで分析され、以下の4項目の評価を中心に行った。
・incorrect weight shift:自身の動きで重心が支持基底面から外れること
・tripping:椅子などなにか外的環境の影響で躓く、支持基底面から重心が外れること
・reaching reaction:上記二つの結果、上肢で何かに掴まろうとした(保護伸展反応)。
・reactive step:支持基底面から重心が外れた結果、下肢のステッピングが生じた。
結 果
・全部で960回の転倒を分析
・パーキンソン病の有する被験者はコントロール群に比べ、1.3倍自身の動きで、1.5倍躓きで転ぶことが多かった。
・パーキンソン病群の約半数(50.7%)の転倒は歩行中に生じた。
・支持基底面から重心が外れたあと、パーキンソン病群は全転倒のうち47.9%にステッピングが生じたが、歩幅がコントロール群に比べて小さいことが多かった。
・パーキンソン病群の上肢保護伸展反応は全転倒のうち36.6%に見られた。そのうち88.9%は把持に成功していた。
明日の臨床アイデア
パーキンソン病の転倒においては、ステップ反応の質を考慮する必要があります。ステッピングが生じたが、歩幅がコントロール群に比べて小さいことが多かったと論文にあります。
例えば、突進現象では、ステップ反応が生じても姿勢を修正しきれていない(ステップにより支持基底面内に重心を戻すことができない)ことなどが要因の一つとなっています。
解決方法は?
1.関節可動域制限など2次的な筋骨格系の問題が生じていないか評価・改善させる
例えば、臥位で十分に万歳の動作はできますか?上半身から十分に伸びることのできる体の柔軟性(肩甲帯〜脊柱の可動性)を獲得することは姿勢(歩容)の改善にも重要です。
2.重心移動・姿勢保持が行えているか?
前後左右への重心移動の切り替えが適切に行えるように練習していきましょう。鏡や壁などリファレンスを用いて姿勢練習することも有用です。重心移動が安定すると、支持基底面の拡張が容易になり、歩幅が増加します。また、特徴的な前かがみ姿勢は加速歩行を助長します。鉛直方向を意識しトレーニングが有用です。
細かなバランスの評価は下のバランステストを参照してください。
その他、歩行時のステップの大きさやその動きの幅を修正・最適化するために視覚的手がかりを用いた訓練は一般的に有効とされる訓練です。
STROKE LAB独自のパーキンソン病体操も転倒予防に有用です。毎日の習慣に取り入れてみましょう。
退院後のリハビリは STROKE LABへ
当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から
以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。


STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)