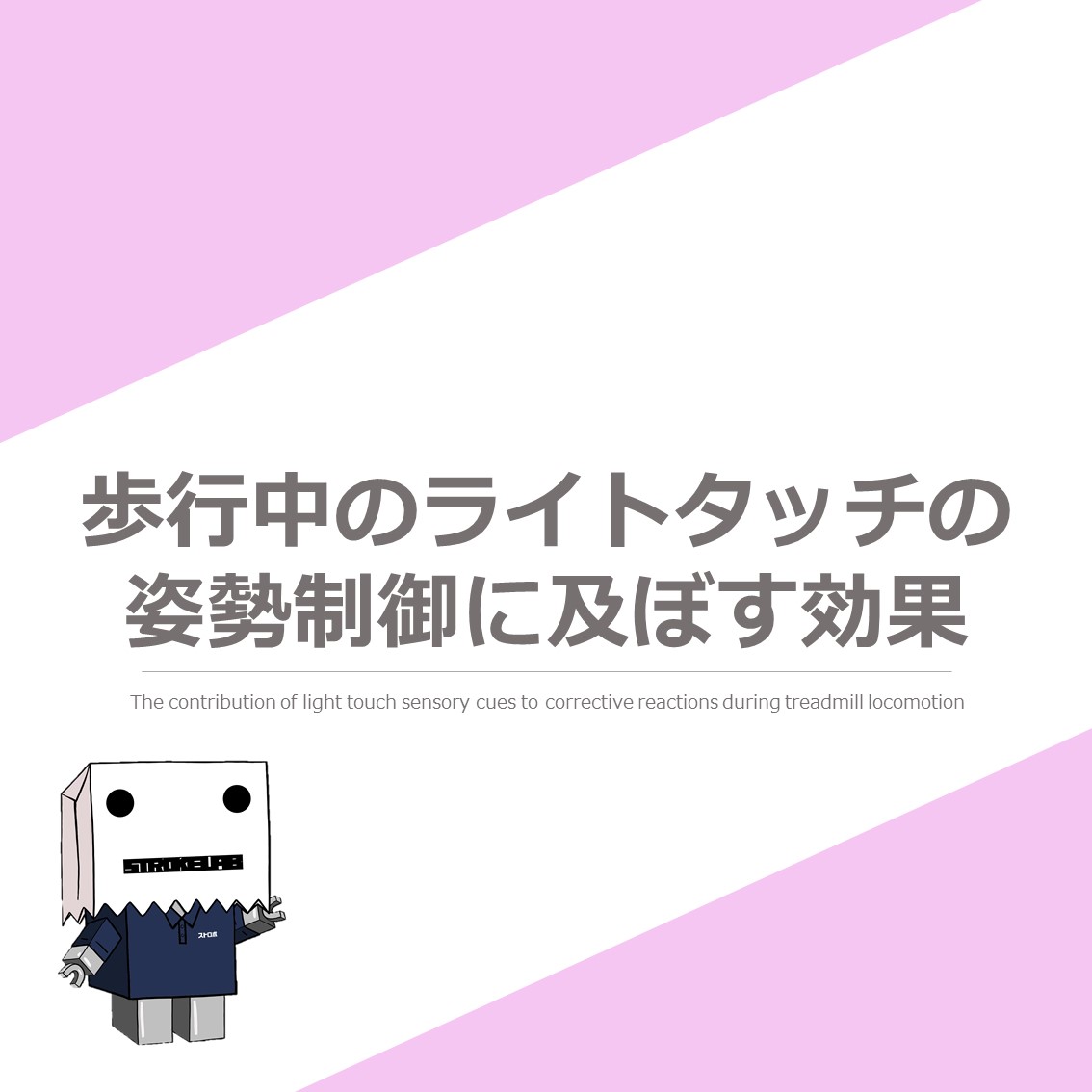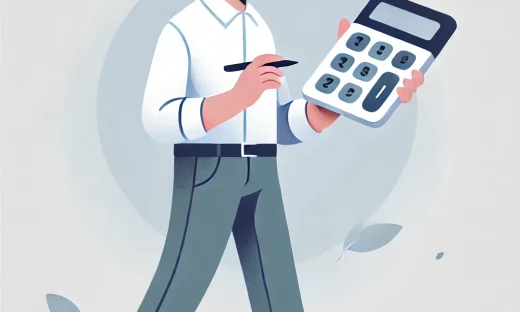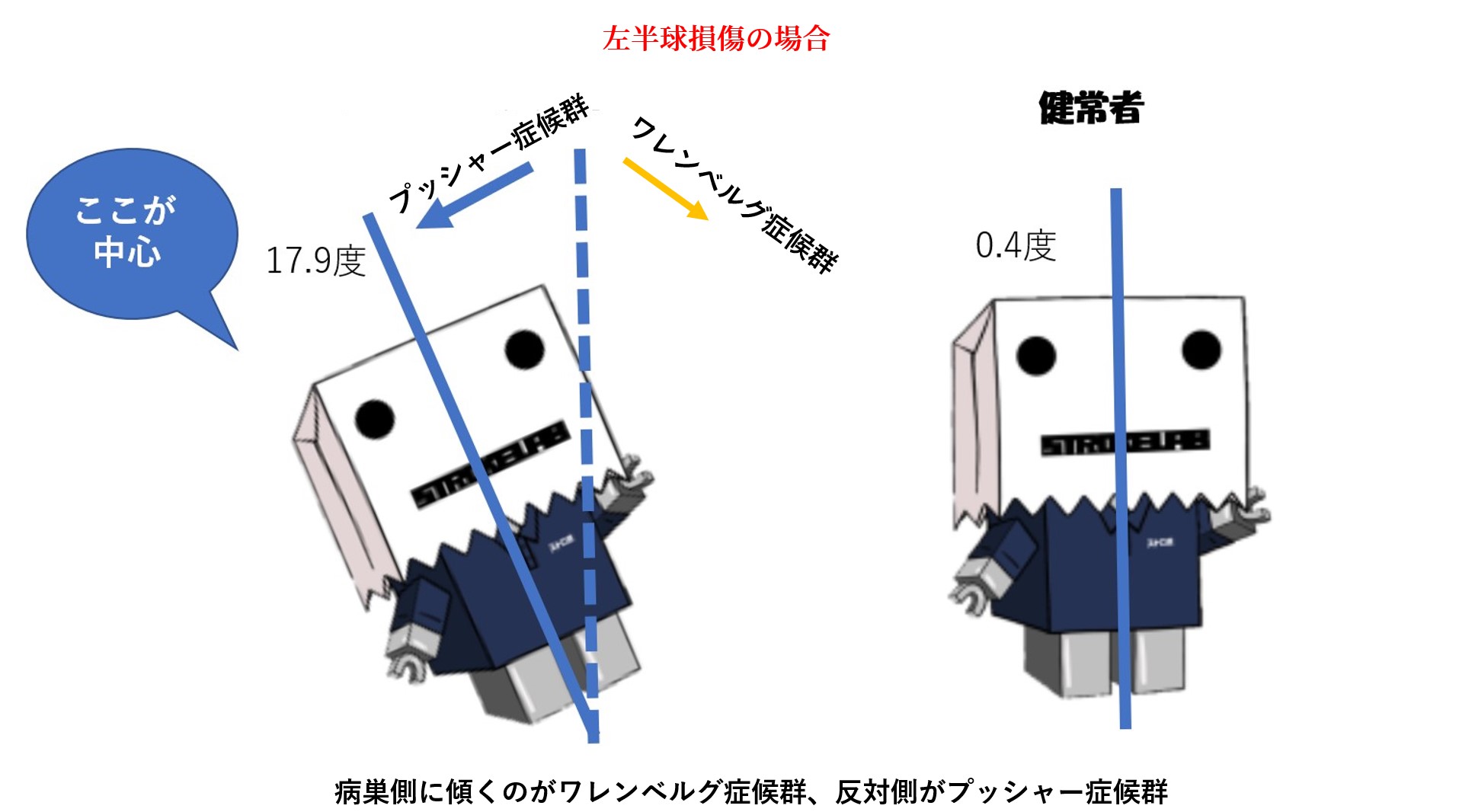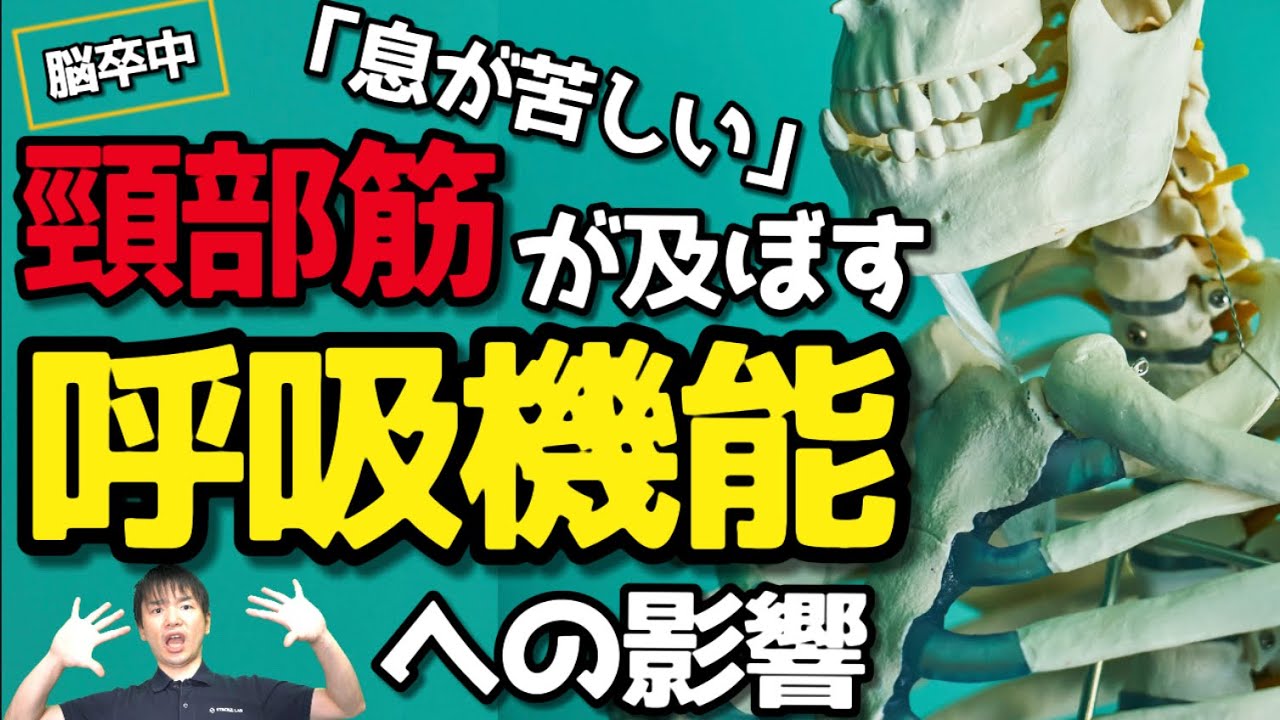【2025年版】脳卒中後に痙縮や痙性はどの筋肉に出現しやすいの?素朴な疑問とエビデンスまで
Q.痙縮とは何ですか?
痙縮(spasticity)は上位運動ニューロン症候群(UMNS)に含まれる速度依存性の筋トーヌス増加で、腱反射の亢進を伴うことが多い(Lance定義)。大脳皮質—脳幹網様体—脊髄の抑制系低下により、脊髄レベルの伸張反射が脱抑制されるのが主要機序です。臨床ではspasticity(伸張反射由来)とspastic dystonia(静止時の持続的過活動)を区別して観察すると、治療標的の明確化に役立ちます。
Q.脳卒中後に痙縮が出やすい筋肉はどこですか?
臨床的には抗重力筋に集中しやすく、典型的な屈曲/伸展シナジーを形成します。
| 発現頻度 | 主な筋群 | ポイント |
|---|---|---|
| 高い | 大胸筋・広背筋・肩甲下筋/上腕二頭筋/前腕・手指屈筋/股内転筋/下腿三頭筋など | ボツリヌス療法の主要ターゲット |
| 中等度 | 上腕三頭筋、前脛骨筋、頸部・腰背部伸筋 | 姿勢・活動量により変動 |
| 低い | 手内在筋、顔面表情筋、小円筋 | 皮質支配が強く痙縮は少ない |
| まれ | 骨盤底筋群(肛門挙筋など)、横隔膜、外眼筋 | 排泄・呼吸障害として顕在化 |
Q.骨盤底筋や肛門挙筋にも痙縮は起こりますか?
理論上は起こり得ますが、四肢のような明瞭な痙縮パターンとしては稀です。脳卒中後は尿失禁・便秘などの排泄失調として現れることが多く、客観評価には内診/EMG/超音波が有用です。
| 視点 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|
| 神経支配 | S2–4陰部神経(随意筋線維)が主。皮質性下行路の直接支配は相対的に弱い。 | 解剖学的事実 |
| 報告例 | 脳卒中後の排尿・排便失調は50%前後に生じ、骨盤底筋再教育が推奨されるが、「痙縮(hypertonia)」としての記載は散発的。 | Care New England |
| 他疾患 | MS・脊髄損傷ではHypertonic Pelvic Floorの記載が豊富。 | Pelvic Rehabilitation Medicine |
| 臨床推論 | 片側大脳病変は骨盤底への直接支配が乏しく、橋排尿中枢などのネットワーク変容により機能的失調(失禁/便秘)が主体。 | 著者見解(文献差あり) |
Q.痙縮をどのように評価すればよいですか?
- 病巣・重症度の把握
- MRI/CT:内包後脚・一次運動野の損傷範囲を定量。CST lesion loadが大きいほど広範痙縮のリスクは相対的に上昇(報告により閾値は異なる)。
- 拡散テンソル:FA値・トラクト整合度で将来の痙縮重症度を推測。
- 臨床重症度:NIHSSやFugl-Meyer(UE)が低いほど痙縮発生のオッズが上がる傾向。
- 筋トーヌス・シナジー計測
- MAS:0–4。2以上は介入の目安。
- Tardieu:V1/V3角度差(R2−R1)で伸張許容量を可視化。R2−R1 < 20°なら軟部拘縮併存を示唆。
- 表面EMG:伸張時RMS上昇(例:>30 µV)を随伴収縮の指標として記録。
- Fugl-Meyer synergy:UEの収束が強いほど屈曲優位パターンを示唆。
- 二次的拘縮の確認
- ROMとMASを併記。ROM先行制限なら構造的短縮優位。
- 超音波エラストグラフィ:拘縮筋のshear modulusは柔軟筋の概ね1.5–2倍。
- 疼痛分離:NRS≧4では保護的収縮が痙縮様に見えるため弁別。
- 骨盤底・体幹の機能評価
- ICIQ-SF/PFDI-20:QOLスコアリング。
- デジタル内診(Glazer分類):4–5は高トーヌス。
- EMG:安静RMS > 4 µV、弛緩遅延 > 3秒は過緊張傾向。
- リアルタイム超音波:肛門挙筋の挙上距離・筋厚変化を観察。
Q.関連データ(サマリ)
| テーマ | 主な知見 | 出典 |
|---|---|---|
| 痙縮の全体有病率 | 1年以内で25–38% | PMC |
| 上肢 vs 下肢同時発現 | 上肢+下肢 27%、上肢単独 8.5%、下肢単独 7.1% | AHA Journals |
| 典型筋パターン | 肩内転・肘屈・手指屈/股内転・足底屈・内反 | Physiopedia |
| 骨盤底機能障害 | CVA後の尿失禁 50%、便秘 48% | Care New England |
| 骨盤底筋Hypertonia | 「短縮し痙性で弱い状態」 | Pelvic Rehabilitation Medicine |
Q.治療・管理のポイントは?
部位別にみると四肢優位痙縮と骨盤底筋機能障害では、介入の狙いと手法が大きく異なります。
| 部位 | 主な介入 | 補足・臨床のコツ |
|---|---|---|
| 四肢優位痙縮 |
|
注射後24–72時間の軟化期に伸張とFESを組み合わせると可塑性が最大化。典型ターゲット:肩内転群、肘屈筋、手指屈筋、腸腰筋、股内転筋、腓腹筋、後脛骨筋。 |
| 骨盤底筋機能障害 |
|
多くは過緊張+弱化の併存。収縮→弛緩誘導→機能課題(排泄タイミング指導)の順で統合。便秘例では温熱や腹部マッサージ併用も検討。 |
Q.まとめ
痙縮は全身の骨格筋で理論上発生し得ますが、臨床の主戦場は抗重力筋です。骨盤底筋群は稀に過緊張として現れうるため、早期スクリーニングと部位特異的アプローチが鍵になります。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)